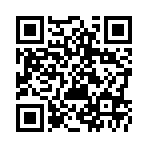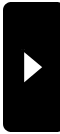2015年06月05日
北九州〜大分潮干狩り情報
 私は新潟の山奥出身の為、30歳くらいまで潮干狩りというモノをテレビでしか見た事がありませんでした。
私は新潟の山奥出身の為、30歳くらいまで潮干狩りというモノをテレビでしか見た事がありませんでした。大分に越してきて直ぐにアサリ掘りに相方と守江湾(杵築)に行ったのですが、憧れと現実は大きく異なり、私には単に砂を掘り続ける労働(笑)としか感じられませんでした。しかも、採ってきたアサリは砂抜きしないと食べられないσ(^_^;)
そんな私にとって転機となったのは調理師学校時代に友人と行った糸ケ浜でのマテ掘りでした。単純労働(笑)ではなく、巣穴を見付ける為だけの最小限の労働+出てくるマテとの駆け引き・・・すっかりはまってしまいました。それからというもの毎年3〜6月は休みと大潮が重なる時は糸ケ浜通い・・・糸ケ浜からマテが居なくなるまでは。
5年程前に糸ケ浜でマテ掘りした時にあまりの採れなさに10年間の個人的禁漁期間を自分で決めました。まぁ大分では数少ない無料の漁場なんで乱獲されちゃうのはしかたないのかもしれませんがσ(^_^;)
すっかりマテ熱は治まっていたのですが、東九州道がほぼ繋がった事で県北〜北九州方面に行きやすくなった上に県北では採りきれない程のマテが居るという情報・・・
そんな事で今年になって試しに行ってみた漁場の情報をご報告します。
その前に、まだマテ掘り未経験の方にマテ貝とマテ掘りの基本的な情報。
 マテ貝は細長い形状の二枚貝で綺麗な砂浜に細長い巣穴を作って住んでいます。貝殻の形状が筒状の為に「砂を噛まない」ので調理前の砂抜きは不要。干潮時に巣穴に塩を入れると浸透圧の関係で飛び出してくる性質を利用して古より採集されてきました。砂浜にできた無数の穴の中からマテ貝の巣穴を判別するのは不可能ですので無差別に塩を入れて行くのは塩の無駄となります。では、どうするのか、実は表面の砂を綺麗に削った時に穴の形状が丸いのはカニ穴(砂浜の表面に見えてる穴の殆どがこれ)菱形というか人の目の様な形をしたのがマテ貝の巣穴です。しかもマテ貝の大きさは穴の大きさで判別できるので無駄に小さい個体を捕まえなくて済むのです。
マテ貝は細長い形状の二枚貝で綺麗な砂浜に細長い巣穴を作って住んでいます。貝殻の形状が筒状の為に「砂を噛まない」ので調理前の砂抜きは不要。干潮時に巣穴に塩を入れると浸透圧の関係で飛び出してくる性質を利用して古より採集されてきました。砂浜にできた無数の穴の中からマテ貝の巣穴を判別するのは不可能ですので無差別に塩を入れて行くのは塩の無駄となります。では、どうするのか、実は表面の砂を綺麗に削った時に穴の形状が丸いのはカニ穴(砂浜の表面に見えてる穴の殆どがこれ)菱形というか人の目の様な形をしたのがマテ貝の巣穴です。しかもマテ貝の大きさは穴の大きさで判別できるので無駄に小さい個体を捕まえなくて済むのです。砂を綺麗に削る道具としてはクワやスコップはたまたプラスチックの下敷きと色々有るのですが、私が使ってみてお勧めなのが「モルタル鍬(左官鍬)」です。ステンレスの棒の先にステン製の20センチ角くらいの板が付いた様な形状なのですが、砂を綺麗に削れる上に軽いし錆び難い。
そして、マテ貝の巣穴を見付けたら塩を穴に掛けるのですが、塩入れとしてお勧めなのが蜂蜜やオリゴ糖の入っている容器。百均のシュガーポットとかでも良いのですが、数をこなすなら蜂蜜容器位のサイズが使いやすいかと。そして、入れる塩ですが5kg入りの普通の食塩をフライパンで一度乾煎りしたのがお勧め。貝掘りに高い塩を買うのは馬鹿らしいですし、食塩でも一度乾煎りしちゃえばサラサラです。熱いうちに容器に入れると容器が変形しちゃうので一度新聞紙の上に広げて冷ますのをお忘れなく。
巣穴に塩を掛けて水がじわじわ出てきたらマテは居ます。すぐに飛び出すのも居ますが、ゆっくりさんもいます。とりあえず先の部分が見えたら少し待ちましょう。それでも出てこない時は素早く先端部分を砂ごと掴んで反対の手で掘って捕獲。掴む時に注意したいのは掴む部分。マテ貝は筒状の形態で竹を縦に割った様な2枚の貝殻をしているのですが、貝殻がすごく薄いので貝殻のアールのついてる部分を掴むと簡単に割ってしまいます。では何処を掴めばいいのか、それは2枚の貝殻の合わせ目部分。ここを掴むとなぜか割れずに力をかける事ができます。
そして、もう一つ大事なのが掴んでも力ずくで引っ張ってはいけないという事。マテ貝の穴の奥側(下側)には「斧足」と言われる砂の中に踏ん張る部分があって無理に引っ張るとそこが千切れてしまうんです。「斧足」が切れちゃいますとマテ貝も弱る(鮮度の落ちが早くなる)上に可食部分の1/3を捨てる事になります。マテ貝を掴んだら軽く引っ張ってみて、踏ん張られたらちょっと待つ・逆に少し穴に押し込む・待たずに反対の手で掘り起こすといった対処が必要となります。
採集したマテ貝は海水入りのバケツに一旦入れておき、帰る時に網袋に移して海水で洗って砂を落とし、綺麗な海水を入れたバケツに網ごと入れて持ち帰ります。熱い時期は車に戻った時点で氷数個を入れたビニル袋を網の上に置いてあげると家まで元気です。
最近は腰痛が酷いのでマテ掘りは子ども達と行って私が砂堀り&塩蒔き・瞬&ほのが捕獲という分業制をとっています。同じように教えたつもりですが兄妹で捕獲スタイルは全く違って瞬は「待ち型」で穴から顔を出すまで絶対手をだしません。ほのは「攻め型」で穴にマテが見えたら即手を出すので仕事が速い代わりに結構な頻度で掴みそこねて逃がしてしまいます(マテ貝は一度掴みかけたら二度と出てこなくなります)。
さて、本題のマテ漁場情報です。
・真玉海岸(大分県豊後高田市)★★★★★
入漁料(大人500円)綺麗なトイレ・水場有り
100%マテしかいない浜。砂は綺麗で掘りやすい荒めの砂。生息数は今まで経験が無い程多く、型も素晴らしいです。マテ掘りの聖地と言っていいと思います。
・和間海浜公園(大分県宇佐市)★★★★
入漁料(小学生300円・大人500円)トイレ・水場有り
潮干狩り専用の浜。アサリ・ハマグリ目当てのお客さんが殆どなのでマテ生息数は多めで型も結構良いです。
・箕島海岸(福岡県行橋市)★★
入漁料(大人500円)そこそこ綺麗なトイレ・水場有り
貝は少なめ、型もそんなに良くない。お客さんが多すぎる。磯も有るので早めに行って潮が引くまでニーナ採りがお勧め。
・白石海岸(福岡県苅田町)★★★
入漁料(無料)ありえないトイレ・水場無し
数は少なめなものの、型はそれなり。貝殻が多くて掘り難い砂。砂の荒い所と細かい所が混ざっていてちょい掘り難い。
・糸ヶ浜(大分県日出町)★
入漁料(無料)トイレ・水場有り
マテだけでなく殆どの貝が取り尽くされた感じ。
客層は箕島90%素人さん、和間50:50、真玉・白石80%ベテランといった感じでした。ベテランになると目的の貝しか採らない(専用の装備)ですし、干潮2時間前には入って食べる分採ったらさっさと帰って行かれます。特にマテ貝は干潮のピークを過ぎると穴から出てきにくくなりますから。
今年は貝掘り行きまくってた所為で5月時点で腕真っ黒&短時間で焼いた為に5月で既に脱皮( ̄▽ ̄;
採ってきたマテ貝ですが、料理方法は炭火焼が絶対のお勧め。砂は全く噛まない貝ですが、水分が多いのでフライパンやホットプレートで焼くと大量の海水を吐くのでマテのほのかな味が消えてしょっぱさだけを強く感じてしまう気がします。炭火焼だと水分が下に落ちるので味が濃く感じられるのだと思います。アサリやハマグリの様に貝自体の味が強い訳でも無く、独特の薄い貝殻の所為で用途も限定される(貝殻ごと他の食材と調理できない)のが欠点といえば欠点かな。
◆マテ掘りお勧め装備
服装:Tシャツ、長ズボン、手拭、アゴ紐付き麦わら帽子、長靴
道具:モルタル鍬、塩(2kg程)&塩容器数個、小型バケツ、網袋、洗車用蓋付きバケツ、塩容器等を入れる小型のリュック、
干潟は日光を遮る物が何も無いので日焼け対策は重要です。ただ、長袖は途中で袖が邪魔になると思いますのでお勧めできません。潮風で髪の毛がガサガサになるので手拭をしてから帽子を被るのをお勧めします。履物はサンダルよりも長靴の方が終えてから履き替えるだけでスッキリできてお勧めです(干潟はアプローチ部分でヘドロ質のとこ通る事も多いので)。
道具は先にいくつか書きましたが、疲れた時の椅子兼用に洗車バケツはお勧めです。背に塩容器の入ったリュック、右手にクワ、左手にバケツと網袋の入った洗車バケツを持って沖へ向かいます。これはと思われるポイントに着いたら「小型バケツ・塩容器・クワ」以外は洗車バケツの上に置いてマテ掘り。食べる分採ったら先の手順でマテを小型バケツに入れてそのまま洗車バケツに入れます。そうすると帰りの車が揺れても車内を濡らさずに済みます(車に載せる前に洗車バケツは真水で砂を流します)。
Posted by toraneko at 21:52│Comments(0)
│季節
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。